令和六年を振り返って

令和六年も暮れようとしております 皆様いかがお過ごしでしょうか 最近はインフルエンザが非常に流行しているようですので 充分お気をつけ下さい
さて 今年も色々なことがありました お寺のことに関して言えば 四月に御小庵と熊王殿の境に崖上から大木が倒れてきて 大きな被害がでました 保険会社の査定に時間がかかりましたが やっと年明けに修復工事が始まります ご迷惑をおかけして申し訳ありません
一方で 二月に樹木葬墓苑「かまくら樹陵 松葉ヶ谷の杜」が開苑したこと そして九月に永代供養墓が完成したことは とても嬉しいことでした 開苑以来予想を超えるたくさんの方にお申込みを頂き 多くの方とご縁を結ぶことができました とても有り難く思っています
当山の樹木葬墓苑の申込手続きの中で 特徴的なことは 面談があることです それは 面接をして申込者の可否を判断するということではなく 最終的な意志決定前に申込者と私が直接会って 色々な話をして多少なりともお互いを理解し スムーズな受入れを図るためです その折には お墓に対するお考えやご家族の状況等を伺うことになります ご遺骨を納めるということは 当山にとってはそれぞれの大切なご家族をお預かりするということです このお寺のことも話しますが 同時に申込者のいろいろな思いを受け止め 安心して任せてもらえるよう精進を重ねなければと身が引き締まります
お寺のこと以外でとりわけ衝撃的だったのが 元日に起きた能登半島地震でした 正月早々あのようなことが起きるとは夢にも思いませんでした 関連の方まで合わせると 犠牲者は五百人を超えると言われております 能登地域には三十四の日蓮宗のお寺があり 本堂も庫裡も全壊したところも多く 全てのお寺が何らかの被害を受けたそうです 年の初めの悲劇にかける言葉がありませんでした 当山でもすぐに義援金の受付を札所で始め 頂いたものを日蓮宗宗務院を通じて被災地に届けました ご協力に深く感謝します また 同じ地域が九月には集中豪雨に見舞われ 十五人の尊い命が失われました 度重なる災害に 自力での復興を諦めたり あるいは他の場所に移ったりと 絶望する人が多いだろうと思っていました しかし そのような中でも 地元で懸命に生きようとされている人が多いことに 私は心を動かされました 世界的に見ても日本は災害の多い国です 加えて 近年の気候変動が原因かもしれませんが 今までの常識では考えられないような厄災が各地で起きています
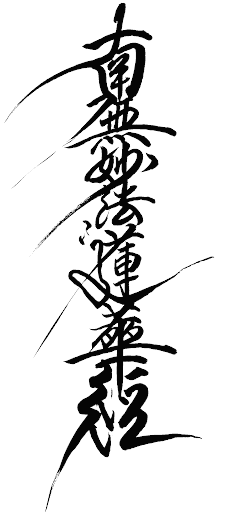
法華経の第三章である譬喩品には このように説かれています 「今此三界 皆是我有 其中衆生 悉是吾子 而今此処 多諸患難 唯我一人 能為救護(今此の三界は皆是我有なり 其の中の衆生は悉くこれ吾子なり 而も今此の処は諸々の患難多し 唯我一人のみよく救護をなす )」現代語に訳せば 「この世は全てお釈迦様の世界であり そこに住む人は皆 お釈迦様の子である この世は色々な悩み 災難 苦しみがある 唯 私(お釈迦様) 一人がそれを救うのである 」となります この世は多くの苦難で満ちています お経によれば それが当たり前の世の中と言えます でも そこで救って下さるのがお釈迦様なのです これは 物理的に救うということではなく 法華経という教えによって 私達の魂を救うという意味です 魂を救うとは お釈迦様が静かに私達の心を気遣われ 寄り添われ 励まされ 導かれ 迷い苦しみのない世界へと迎え入れて下さり そのことによって 永遠で最高の幸せを得ることと考えます このような意味で 法華経を読み 「南無妙法蓮華経」とお題目をお唱えすることは お釈迦様の教えや導きを心の中に入れることであり 救いへの道を進むことです
日蓮聖人は お題目とは法華経の全ての功徳を含んだものであると説かれています 日蓮聖人の教えは 亡くなった人のためだけではなく 生きている私達のためのものでもあります この世で生きている私達を救う教えです 「南無妙法蓮華経」とお唱えする時 私達は慰められ 活力を与えられ 向かうべき方向を示されます
テレビなどで よく自分は無宗教だとインタビューに答える人を見ます 無宗教といいながらも 大きな被害に遭うと 神様か仏様かに助けを求めているのではないでしょうか その時に誰に助けを求めればよいのか 誰が助けてくれるのか 漠然と誰かにではなく ちゃんと助けてくれる方に祈ることが必要です ちゃんと助けて下さるのは お釈迦様であり 祈りの言葉はお題目 南無妙法蓮華経です 平穏な時も非常時も 嬉しい時も悲しい時も お題目をお唱えすることが大切です そうしてお題目と共に生きることによって 何時いかなる時も私達は救われていきます
本年も大変お世話になりました 心から御礼申し上げます 来る令和七年が皆様にとり実り多き一年となりますようお祈り申し上げます
合掌
2024年12月31日
